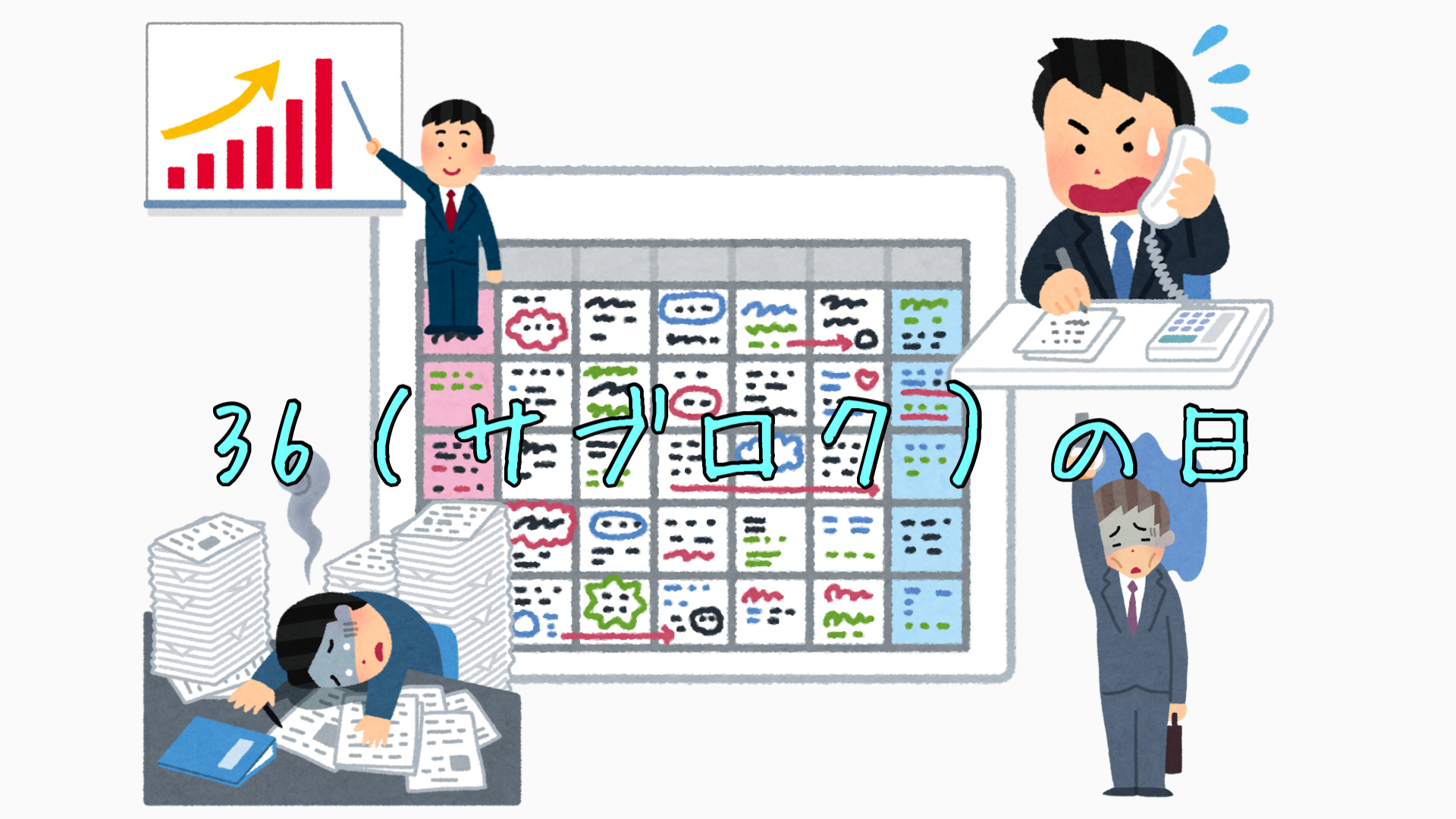毎年3月6日は、「36(サブロク)の日」として知られています。この記念日は、労働基準法第36条に基づく「36協定」に由来しており、日本の労働環境において重要な意味を持っています。本記事では、36(サブロク)の日の由来や36協定の役割、働き方改革との関係、企業や労働者が取るべき対策について詳しく解説していきます。

36協定?どんな内容なのかしら
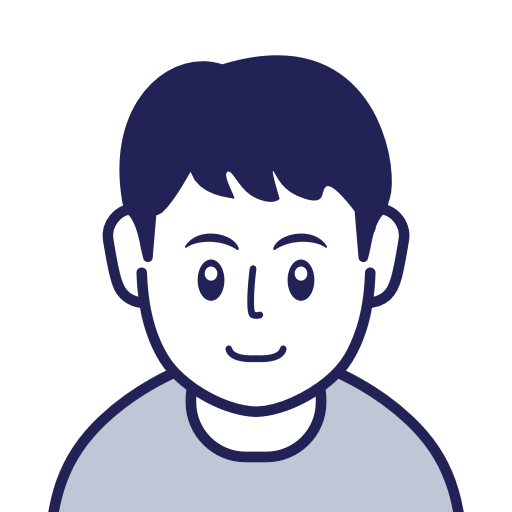
36協定を理解するために次の記事を読んでみよう!
36(サブロク)協定とは?
36(サブロク)協定とは、労働基準法第36条に基づき、企業が従業員に法定労働時間を超えて残業や休日労働をさせる際に労使間で締結する協定のことを指します。日本の労働基準法では、原則として1日8時間、週40時間の労働時間が定められていますが、36協定が締結されていれば、この時間を超えて働くことが可能になります。
ただし、36協定は無制限に時間外労働を認めるものではなく、労働基準法や関連する労働行政のガイドラインによって、時間外労働の上限が厳しく規定されています。特に、2019年4月から施行された「働き方改革関連法」により、時間外労働の上限が明確化されました。

そもそも決められている労働時間を超えて仕事ができるのね。
でも、それだけでは怖い協定に見えるわ。
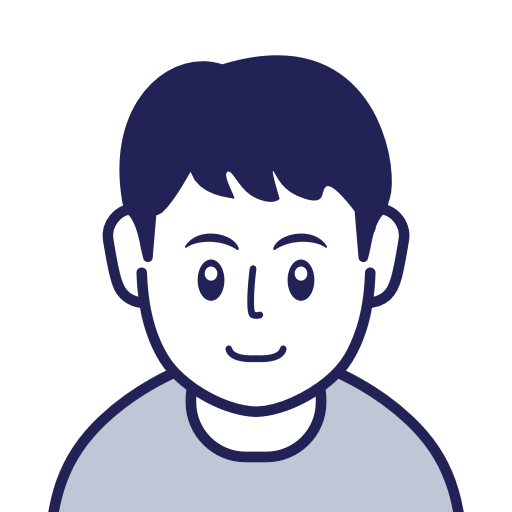
記事内容にもあるように、無制限に働かせるブラック会社を産まないために事前に「36協定届」を提出しなければならないから、安易に使用できない協定なんだよ。
36(サブロク)の日の由来
「36(サブロク)の日」は、労働基準法第36条の周知と、適正な労働時間管理の重要性を再認識するために制定されました。特に、長時間労働が社会問題となる中で、企業や労働者が36協定の意義を理解し、適切な働き方を推進することが求められています。
この記念日を機に、多くの企業が労働時間の適正管理や、業務の効率化、ワークライフバランスの向上に向けた取り組みを強化することが推奨されています。
36協定と働き方改革の関係
近年、日本では「働き方改革」が推進されており、その中でも長時間労働の是正が大きなテーマとなっています。36協定は、適正な労働時間の管理において重要な役割を果たすため、以下のような点で働き方改革と深く関わっています。
1. 残業時間の上限規制
働き方改革関連法により、36協定のもとでの時間外労働の上限が厳格化されました。具体的には、
- 月45時間、年間360時間を原則とする。
- 特別条項付き36協定を結んだ場合でも、
- 年720時間以内
- 1か月100時間未満
- 2~6か月平均80時間以内 、という上限が設定されました。

残業時間が2倍に増えるけど、平均残業時間に月数規制を設けて長期的に働きすぎないようにしているのね。
2. 労働生産性の向上
長時間労働を減らすためには、単に労働時間を短縮するだけでなく、労働生産性の向上が必要です。そのため、多くの企業では、
- IT技術の活用
- 業務プロセスの見直し
- テレワークやフレックスタイム制度の導入 など、効率的な働き方を模索しています。
3. 健康管理と労働環境の改善
長時間労働は、従業員の健康にも悪影響を及ぼします。過労死やメンタルヘルスの問題を防ぐため、企業は従業員の健康管理にも力を入れる必要があります。
企業と労働者が取るべき対策
企業側の対策
- 労働時間の適正管理
- 勤怠管理システムを導入し、労働時間を正確に把握する。
- 残業の事前申請制を導入し、不必要な時間外労働を防ぐ。
- 業務の効率化
- RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)などの自動化技術を活用し、業務負担を軽減する。
- 業務の見直しを行い、無駄な作業を削減する。
- ワークライフバランスの推進
- ノー残業デーの実施
- フレックスタイムやリモートワークの導入
- 有給休暇の取得促進
労働者側の対策
- 労働時間の自己管理
- 無駄な残業をしないよう、業務の優先順位をつける。
- 休憩を適切に取り、メリハリのある働き方を意識する。
- スキルアップとキャリア形成
- 効率的に仕事をこなせるよう、必要なスキルを学ぶ。
- キャリアプランを明確にし、将来の働き方を考える。
- 健康管理
- 適度な運動や栄養バランスの取れた食事を心掛ける。
- ストレスを溜めすぎないよう、趣味やリラックスの時間を大切にする。
まとめ
3月6日の「36(サブロク)の日」は、労働環境の改善を考える重要な機会です。36協定の意義を理解し、適正な労働時間管理を徹底することで、より良い職場環境を築くことができます。
企業も労働者も、お互いに協力しながら、働きやすい環境を整えていくことが求められています。この機会に、自身の働き方を見直し、より良いワークライフバランスを実現しましょう!
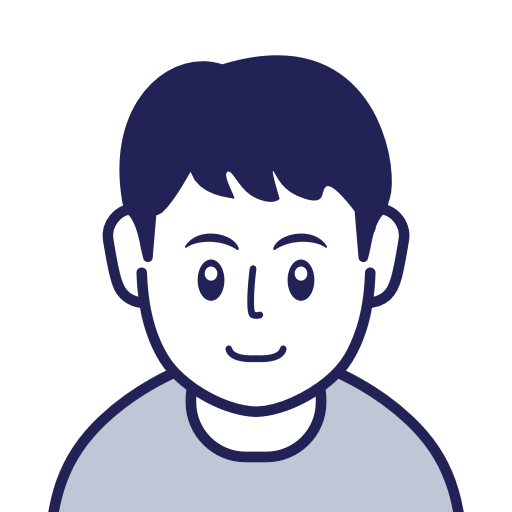
無茶しない程度に働こう!